個人事業主にだけある制度!専従者給与控除をご紹介
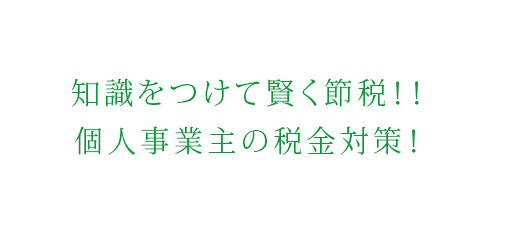
 個人事業主は家族への給与を経費にできる
個人事業主は家族への給与を経費にできる
個人事業主は、専従者給与といって、家族への給与を経費に計上することができます。個人事業主にだけある制度です。家族に給与を支払っても、通常は経費にならないのですが、一定の手続きをして、基準を満たしていれば、その支払分が経費になります。手続きは、白色申告のときは必要ありませんが、青色申告のときは、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。提出の期限は、給与を払う年の3月15日までになります。
「専従者」とは、個人事業主と一緒に生活をしている配偶者、親、祖父母、や15歳以上の子供などのことです。「生計を一にしている」と言い、ただ同居しているだけではなく、家計を一緒にして、暮らしているという意味です。ただし、その家族が会社員などとして働いている場合、専従者としての給与をもらうことはできません。そして、専従者として働く場合は、1年のうち半年以上は、その個人事業主の仕事に就いていなければなりません。
給与の金額は、申告の方法によって、限度額が変わります。白色申告のときの限度額は、配偶者は86万円、配偶者以外は50万円となります。白色申告しているときには、家族がどれだけ長時間労働しても、最高で、この金額までしか給与として出すことができません。青色申告のときは、限度額を届出書に記載することができるため、いくらでも出そうと思えば出すことができます。事業の利益をゼロにするような設定も可能です。一番効果的な金額設定は、利益が100万円以上になる見込みのときは、事業主と専従者の2人の所得が同じになるような金額(事業利益の半分)です。これは、所得税の税率が所得が高ければ高いほど税率が高くなるので2人の所得を平均化したほうが税金が安くなるからです。ただし、この基準は、双方の扶養の状況や社会保険の関係などで、変わってくることもあります。利益が100万円未満になる見込みのとき、毎月8万8千円がよいでしょう。この金額はもらった人にも税金が発生せず、かつ、経費にできる最高金額となります。
給与として支払うので、もちろん労働してもらわなくてはなりません。家族であっても、きちんとした勤務実態が必要です。実際に個人事業主と同じ仕事をしている方は全く問題がありませんが、普段は、専業主婦で配偶者のサポートをしている方も多くいます。一般的には、現場の業務でなくても、以下のような業務を行っていれば、専従者給与として認めてもらえるようです。個人事業者の記帳、領収書の整理、請求書の発行、経理関係業務、個人事業主のスケジュール管理、顧客の電話応対、来客応対、お茶出し、メール管理、データ管理、備品管理、調査、調べ物、書類整理、片付け、その他事業に係る付属業務などでしょうか。税務署の調査を意識して事業を手伝っている記録や証拠があればよいでしょう。
 個人事業主の節税対策を考えるなら、何はともあれ「経費」を一通り見直してみましょう!「事業に必要な支出」が経費として認められるわけですが、個人事業主にとって事業に必要な支出とはどのようなものが該当するのでしょうか?逆に、「経費に出来ないもの」として何か決められている項目はあるのでしょうか?ざっと目を通してみましょう。もしかしたら、今まで計上していなかったけど、実は計上できるような経費が見つかるかもしれません。 個人事業主で経費に出来ないものの詳細を見る
個人事業主の節税対策を考えるなら、何はともあれ「経費」を一通り見直してみましょう!「事業に必要な支出」が経費として認められるわけですが、個人事業主にとって事業に必要な支出とはどのようなものが該当するのでしょうか?逆に、「経費に出来ないもの」として何か決められている項目はあるのでしょうか?ざっと目を通してみましょう。もしかしたら、今まで計上していなかったけど、実は計上できるような経費が見つかるかもしれません。 個人事業主で経費に出来ないものの詳細を見る
 個人事業主の退職金といわれる、小規模企業共済を知っていますか?個人事業者が事業を廃止したときのために積み立てておける共済制度です。掛け金は毎月1,000円という小さな額から設定できて、500円単位で増額できます。この小規模企業共済の掛け金も、控除の対象になるのです。共済金として積み立てたお金は後で自分に戻ってきます。税金として支払うよりも断然お得ですよね。個人事業主の賢い節税対策として、使える控除は使いましょう。 個人事業主は小規模企業共済でお得に控除の詳細を見る
個人事業主の退職金といわれる、小規模企業共済を知っていますか?個人事業者が事業を廃止したときのために積み立てておける共済制度です。掛け金は毎月1,000円という小さな額から設定できて、500円単位で増額できます。この小規模企業共済の掛け金も、控除の対象になるのです。共済金として積み立てたお金は後で自分に戻ってきます。税金として支払うよりも断然お得ですよね。個人事業主の賢い節税対策として、使える控除は使いましょう。 個人事業主は小規模企業共済でお得に控除の詳細を見る
 個人事業主から法人化を検討するにあたって、税金はどう変わるのか?というのも大変気になるポイントですね。法人になれば当然、税金のルールも仕組みも変わってきます。法人化することによって納税額が増えるケースもありますし、どちらがお得かは一概には言えません。まずは、個人事業主の税金と法人の税金、それぞれの違いについて理解を深めておきましょう。法人化することで得られるメリットとデメリット、そして税金の差などをよく比較検討することをオススメします。 個人事業主と法人の税金の違いの詳細を見る
個人事業主から法人化を検討するにあたって、税金はどう変わるのか?というのも大変気になるポイントですね。法人になれば当然、税金のルールも仕組みも変わってきます。法人化することによって納税額が増えるケースもありますし、どちらがお得かは一概には言えません。まずは、個人事業主の税金と法人の税金、それぞれの違いについて理解を深めておきましょう。法人化することで得られるメリットとデメリット、そして税金の差などをよく比較検討することをオススメします。 個人事業主と法人の税金の違いの詳細を見る